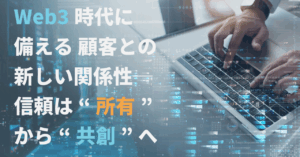シェア・応援”が起点になる価値経済への対応─ つながりが価値になる時代のマーケティング戦略
売れないのは、仕組みが“足りない”のではなく“違っている”のかもしれない。
「毎日SNSで発信しているのに、なぜか売上につながらない」
「広告も試してみた。でも“いいね”は増えるのに、結果は変わらない」
──そんな経験はありませんか?
それは、あなたの熱量や努力が足りないのではなく、
時代が変化していることに、設計が追いついていないだけかもしれません。
💡 いま、売上は“機能や価格”ではなく「応援」から生まれています。

マーケティングの主役が「売ること」から「応援されること」へと移りつつある今──
キーワードは「価値経済」。
つまり、人々の感情・共感・つながりが、購買の起点になる時代です。
- 「この人を応援したい」から購入する
- 「このストーリーを広めたい」からシェアする
- 「関わっていたい」から継続する
こうした行動が、**広告よりも強い信頼と拡散力を持つ“仕組み”**になっています。
🎯 この記事で届けたいこと
この第43章では、単なる共感だけで終わらせない──
**「応援が自然に起き、拡がる構造のつくり方」**を解説します。
✔ 読んでもらいたい方
ファンはいるのに売上に直結しないことに違和感を抱えている方
SNS・ブログで発信をしているが成果が見えないフリーランス・個人事業主
クチコミや紹介で「自走する仕組み」をつくりたい小規模ビジネス
第1章|応援が“価値”になる時代の始まり
─「売れていない」のではなく「応援されていない」だけかもしれない
「SNSのフォロワーは1万人。でも、売れない」
「LINE登録は増えた。でも、商品が動かない」
「広告を出してみた。でも反応がない」
マーケティングの現場では、こんな“空回り”の声を多く耳にします。
一見、仕組みは揃っている。行動量もある。それなのに──なぜか成果につながらない。
その理由は、「やっていない」からではなく、
“時代に合った構造になっていない”からかもしれません。
🔁 売ることから、応援されることへ
今、ビジネスの価値は「売れたかどうか」よりも、
「誰に応援されているか」「どれだけ共感されているか」に移りつつあります。
- フォローされているけれど、誰にも語られていない
- 商品は良いけれど、ストーリーが伝わっていない
- 一度買われたけれど、次につながらない
これらはすべて、“応援が起きていない状態”と見ることができます。

💬 「応援」は感情の投票であり、経済活動である
クラウドファンディングの支援、メンバーシップ課金、SNSでのシェア──
一つひとつは小さなアクションでも、それが重なれば大きな“価値”になります。
・モノを買うのではなく、活動を応援する
・サービスを選ぶのではなく、人を信頼して関わる
つまり、「買う理由」が“価格や機能”から“意味や関係性”に変わっているのです。
🔍 変化の本質に気づかないまま、“旧来の売り方”を続けていないか?
多くの事業者が、「仕組みが足りない」と感じてツールを増やし、施策を増やします。
でも本当に必要なのは、新しい設計図です。
これからの時代に求められるのは、
「応援される仕組みを“設計”する」
という視点なのです。
このあとの章では、
● 売れている人が実は「やっていないこと」
● 応援が起きる心理の構造
● 応援されるブランドの設計方法
などを、順に解説していきます。
第2章|売れている人が“していないこと”
──仕組みより「信頼される場」をつくっている
「この人、あまり売り込んでないのに売れてるな…」
「広告も打ってないのに、紹介が絶えない」
そんな“売れている人”には共通点があります。
彼らは、実は多くの「施策」をしていません。
それは怠惰ではなく、本質だけに集中しているということ。
ここでは、売れている人が「やっていないこと」から見える、
“応援される仕組みの本質”を掘り下げます。
✅ 売れている人が、意外とやっていないこと
| やっていないこと | 理由(または代替手段) |
|---|---|
| 毎日売り込み投稿 | ➤ 売り込まずとも「語られる設計」を持っている |
| 値引きキャンペーン | ➤ “信頼”が価値になっているので価格競争に巻き込まれない |
| アルゴリズム攻略だけの投稿設計 | ➤ 共感・物語・つながりを重視した発信で“応援される” |
| 売れる商品ばかりを作る | ➤ “存在”や“価値観”に共感が集まり、何を出しても支持される構造 |
🧠 応援される人がやっていること:感情設計 × 関係性構築
一方で、売れている人がやっているのはこんなことです:
- 商品より先に「信頼の土台」を築いている
- 発信で“共感”や“物語”を共有している
- 小さな応援(コメント、シェア)に対して丁寧に反応している
- 「みんなで育てる」空気感を、あえてつくっている
彼らの発信は、売るためではなく“関わってもらう”ために設計されています。
📌 事例:売れている個人デザイナーの例
あるデザイナーは、制作実績よりも「その作品に込めた想い」を丁寧に発信しています。
彼女は特別な営業活動はせず、ただ「想いと過程」を日々、共有しているだけ。
にもかかわらず──
- noteで紹介される
- SNSで自然に広まる
- 「紹介されて知りました」と新規依頼が届く
つまり、「売らない」ことで逆に“応援される場”が育っているのです。
💡 施策より“関係性の質”が売上を決める
たくさん施策を打っているのに売れないときは、
「やっていないこと」が問題なのではなく、
“やらないと決めていること”が間違っているのかもしれません。
次章では、こうした流れの土台となる
「価値経済」の構造と、“応援が通貨になる時代”の背景を図解付きで解説していきます。
第3章|価値経済とは何か?
──「共感と信頼」が通貨になる時代の構造
かつて「価値」は、価格や機能のことでした。
良い商品・優れたサービス・合理的な価格。
それが「選ばれる理由」であり、売上を生む源でした。
しかし、今やSNSやコミュニティ、クラウドファンディングの登場により、
**「誰が、どんな想いで、どんな物語を届けているか」**が価値になる時代が到来しています。
この新しい経済圏は「価値経済」と呼ばれ、
お金ではなく共感・信頼・関係性が循環の核になっています。
💡 「いいね」や「シェア」が“経済行動”になる
あなたがSNSでシェアしたり、クラファンで投げ銭をしたり、
あるいは「応援してます」とコメントする行為は──
見返りを求めない感情の表現であり、
相手にとっての“信用通貨”として機能している
つまり、「いいね」や「シェア」は、
その人(ブランド)を選び、認め、他者へ広げる投票行動なのです。
🔁【図解イメージ】価値経済の基本構造(文章で表現)
共感 → 応援 → 拡散 → 信頼 → 継続 → 新たな価値創出
↑ ↓
←─── 循環する「関係性資産」 ───→
ここでは“共感”が起点であり、
“お金の前に心が動く”という順序で購買が成立します。
この循環が強いブランドほど、「売る前に選ばれ、語られ、広がる」のです。
✅ “機能”より“関係性”が選ばれる例
| 時代 | 購買の動機 | 重視される価値 |
|---|---|---|
| 旧来 | コスパ・機能 | 性能・価格・利便性 |
| 現在 | 応援・共感 | ストーリー・信頼・関係性 |
📌 実例:note、Instagram、クラファンで見られる共通点
- note:「この人の考え方が好き」だから有料記事が売れる
- Instagram:「日々の発信に共感している」からグッズが売れる
- クラファン:「この活動を応援したい」から商品が届く前に支援する
これはまさに、感情→応援→経済行動という「価値経済の構造」が機能している状態です。
💬 共感は“無料”で得られるものではない
「感動してもらえれば売れる」「共感してもらえれば自然に広まる」
──それは幻想です。
共感は“戦略”であり、“設計”で生まれます。
だからこそ、次章では**「なぜ人は応援したくなるのか?」**という感情設計の仕組みを、心理トリガーの観点からひもといていきます。
第4章|なぜ人は応援したくなるのか?
── 感情を動かす3つの心理トリガー
「この人の活動、なんだか応援したくなる」
「気づけば、毎回いいねやシェアをしている」
──あなたにも、そんな“気づけば支援している”体験はありませんか?
応援とは、単なる好意ではありません。
共感・所属・影響といった感情が動いたときに、人は自然と“関わりたくなる”のです。
この章では、応援が生まれる3つの心理的トリガーを解説します。
✅ トリガー1|「所属したい」:共通する価値観・世界観への参加
人は、“自分の居場所”や“つながり”を感じられる場所に価値を感じます。
- 同じ悩みを抱えていた過去
- 自分の生き方や働き方に通じるテーマ
- 「この人の活動に、自分も関わっていたい」と思える世界観
たとえば、発信者が「一人でがんばっているフリーランスの苦労」を語ったとき、
その経験に“自分を重ねた”読者は、単なる読み手から当事者的な応援者へ変化します。
✅ トリガー2|「共感したい」:物語・葛藤・過程への感情接続
応援される人の多くは、「成功談」よりも「未完成な挑戦」を見せています。
- うまくいかなかったこと
- 一歩ずつ積み重ねてきた過程
- 背景にある想いや、見えない努力
こうした“物語性”は、見る者に感情のフックを生み、
「この人を応援することが、自分の原動力にもなる」
という内的な動機へと転化します。
✅ トリガー3|「影響したい」:応援によって貢献・拡散できる快感
人は「誰かの役に立てた」と感じたとき、大きな充足感を覚えます。
- リツイートしたら、誰かから「ありがとう」と言われた
- クラファンを支援したら、自分の名前がページに載った
- 感想を投稿したら、クリエイターが返信をくれた
こうした“関与の体験”が「もっと応援したい」という意欲を加速させます。
これは、応援者自身が“物語の登場人物になる”体験でもあります。
🔄【図解イメージ】応援が生まれる3ステップ(文章で再現)
① 所属したい → ② 共感したい → ③ 影響したい
↓ ↓ ↓
世界観に参加 物語に感情移入 行動によって意味を実感
この3つの感情が揃ったとき、
応援は「偶発的なアクション」から「自発的な習慣」へと進化します。
📌 補足:応援を引き出すには、“余白”が必要
完璧な発信、完成された商品、隙のないブランドは、
「すごい」と思われても「応援したい」とは思われません。
応援は、「余白」や「未完成」に生まれます。
だからこそ、“関わる余地”をあえて残す設計が求められるのです。
次章では、この3つの感情トリガーを踏まえ、
**「応援されるブランドが実践している設計」**の共通点を深掘りしていきます。
第5章|応援されるブランドの設計術
── 共感を“仕組み”に変える技術
共感された、感動された──それだけではビジネスは動きません。
大切なのは、その感情を「行動」や「拡散」につなげる構造的な設計です。
この章では、応援され続けるブランドが実践している「共感を仕組みにする技術」を、3つの視点で解説します。
✅ 設計1|“共感できる”ではなく、“語りたくなる”発信を設計する
ブランドの価値を伝えるとき、よくある間違いが「自分の魅力を丁寧に語りすぎること」です。
応援される人たちは、自分を語るより、**“相手が語りたくなる要素”**を設計しています。
- ストーリーに「共通する課題」や「過去の自分」を含める
- 読み手が“自分のことのように”感じられる比喩や例を使う
- 「この話、誰かに教えたい」と思わせるエピソードで構成する
💡Point:「発信のゴールは“共感”ではなく、“再解釈”と“拡散”である」
✅ 設計2|“関わりしろ”を設けることで、応援を“体験”にする
応援とは、リアクションではなく“体験”です。
ただ投稿を読むだけではなく、「関われた」と思える接点をいかに設計できるかが鍵になります。
具体的には:
- コメント欄や感想投稿を歓迎する文化づくり
- 名前を呼ぶ、お礼をする、小さな貢献を拾い上げる
- アンケートや意見募集で「場に関われた感覚」を与える
これにより、読者は**“自分がこのブランドの一部だ”**と感じるようになります。
✅ 設計3|“語られる余白”をあえて残す
全てを説明しない。完璧に見せない。
これはマーケティングにおいて、実はとても有効な技術です。
- ブランドの価値観に“あいまいな共通点”を持たせる
- 過程や迷い、試行錯誤を共有する
- 「一緒に育てていこう」というスタンスを示す
応援は、「自分も関わっている」と思える“余白”から生まれる。
これはクリエイターや起業家だけでなく、企業ブランドにも通用する重要な視点です。
💬 補足:フォロワーではなく「語り手」を育てる視点へ
SNSやメルマガでの発信は、**単なる情報提供ではなく“語り手を育てる場”**です。
フォロワーに「見てもらう」ではなく、
読者に「語ってもらう」設計をすることで、ブランドは“共感の渦”を育てていけます。
次章では、この応援の熱量がどのようにシェアされ、拡散されるのか?
その仕組みを設計する【第6章|シェアされる導線のつくり方】に進みます。
第6章|シェアされる導線のつくり方
── 共感を“拡げる”仕組みと仕掛け
「共感はされた。でも、誰にも伝わっていない」
そんな状態は、今の時代ではとてももったいないことです。
なぜなら、“共感”は「その場の感動」で終わらせるのではなく、
“シェアによって別の誰かに届く”ことで、初めて影響力を持つからです。
この章では、「いい話だったね」で終わらせず、
「この人のこと、誰かに伝えたい」と思ってもらえる導線設計を紹介します。
✅ 導線1|“シェアの理由”を明文化する
多くの読者は、「よかった」と思っても、
「なぜシェアするのか?」の理由を言語化できないと行動に移しません。
だからこそ、発信側が次のように**“共感の言語化”を代行**します:
- 「これ、同じ立場の人に届いてほしい」
- 「あの時の私にも読ませたかった」
- 「この話、あなたなら共感してくれると思った」
▶ これを本文やCTAにあえて記述することで、読者の“脳内の説明”を補って行動を促せます。
✅ 導線2|“シェアしやすさ”を設計する
どんなに感動しても、投稿の導線がなければ人は動きません。
たとえば:
- 「#○○の感想」で投稿してね、という一言
- X(旧Twitter)投稿例のテンプレを用意
- noteやブログなら「スキ」「コメント欄」「拡散ボタン」周辺の導線整理
💡Point:**「行動を1クリックで済ませられる設計」**がシェア率を左右します。
✅ 導線3|語り手が“主役になる設計”を仕込む
応援したい気持ちと同じくらい、「誰かの役に立てた」と思える体験は貴重です。
そのためには:
- 感想投稿に反応する
- 記事中に読者の言葉を引用する(共創)
- 「あなたの声が届きました」的なリアクションを用意する
▶ シェア=自分もこの物語の一部だ、と思える設計を仕込むことで、
“語る人”を生み出す導線が完成します。
📌 チェックリスト:あなたの導線、シェアされやすいですか?
| チェック項目 | Yes / No |
|---|---|
| シェアのきっかけとなる言葉が明示されているか? | ✅ / ❌ |
| SNS投稿用テンプレやハッシュタグが用意されているか? | ✅ / ❌ |
| 読者が登場人物になれる“余白”が存在するか? | ✅ / ❌ |
| 感想への返信・紹介など「関与の場」があるか? | ✅ / ❌ |
次章では、こうした「応援→シェア→拡散」の設計をさらに超えて、
“長く応援され続けるブランド”の共通点を掘り下げていきます。
第7章|“長く応援されるブランド”の共通点とは?
── 応援を“習慣”に変える関係設計
一度は共感された。シェアもされた。
でも、次の投稿では静かになった。
こうした“一過性の応援”に終わらせないために、
本当に大切なのは、**「応援され続ける設計」**です。
応援とは、信頼関係と似ています。
小さなやり取りの積み重ねで深まり、日常の一部になったとき──
それは“習慣”になります。
この章では、そんな**“長く応援されるブランド”が実践している設計の共通点**を解説します。
✅ 共通点①|定期的な「感情の再接続」を行っている
どんなに感動されたとしても、時間とともに熱量は下がっていきます。
だからこそ、定期的に“初心に戻る”発信や体験の提供が重要です。
- あらためてブランドの背景や想いを語る
- ファンや顧客の声をフィードバックとして紹介する
- 月初や節目に「この活動に込めた願い」を再発信する
▶ これにより、“そうだった。この人を応援したいんだった”という気持ちをリフレッシュできます。
✅ 共通点②|変化の共有を惜しまない
応援している側が冷めてしまう原因のひとつは、「動きが見えない」ことです。
つまり、関係性が停滞して見えると、応援が“止まる”のです。
- 進捗・苦悩・アップデートなどをリアルタイムで共有
- 感情を交えた“裏話”を届ける
- 目標の途中経過を公開し「一緒に進んでいる感覚」を持ってもらう
▶ 大切なのは、「成果」ではなく「過程」を一緒に歩めること。
ブランドの“成長ドラマ”を追うこと自体が、応援のモチベーションになるのです。
✅ 共通点③|ファンに「役割」がある
応援とは、本来“能動的な行動”です。
そのためには、“何か自分にもできることがある”という参加感が鍵になります。
たとえば:
- メンションでの紹介をお願いする
- 自分の言葉で感想を書く機会を設ける
- フィードバックを次の施策に取り入れることで“共創感”を持たせる
▶ こうした仕掛けにより、応援者=共犯者・共作者という関係性が育ちます。
💬 補足:小さな感謝が、応援を続けさせる
「応援してよかった」と思ってもらうこと。
それは、ギフトを贈ることでも、特別な報酬でもありません。
- 感想へのリアクション
- 「見てます」「ありがとう」のひと言
- 応援者の名前や声を投稿内に取り上げる
▶ こうした“非金銭的報酬”こそが、「また応援したい」という感情を引き出します。
第8章|応援は“売上を超える資産”になる
── これからのマーケティングが向かう場所
ビジネスにおいて「売上」は、確かに大切な指標です。
でも、それ以上に長期的な価値を持つのが──
「関係性の資産」、つまり“応援される状態”です。
応援とは、商品が売れたその瞬間だけの行為ではありません。
時間とともに“ブランドの土台”として積み重なっていく無形資産なのです。
✅ 応援には「再現性」がある
広告を出して得た売上は、一度限りかもしれません。
でも、応援される仕組みをつくれば──
- 新しい商品を出しても買ってもらえる
- シェアされ、自然と新規顧客に届く
- 応援者が“布教活動”をしてくれる
つまり、「1人が10人を連れてくる」仕組みが生まれます。
これは広告以上に強い、**“人が人を動かすマーケティング”**です。
✅ 応援がもたらす、3つの「売上を超える価値」
- 信頼という“選ばれ続ける力”
→ 競合が増えても「この人にお願いしたい」と思ってもらえる - 共創という“進化の原動力”
→ ファンの声や反応が、次のアイデアを生むヒントになる - 循環という“自走する仕組み”
→ 自分が発信しなくても、応援者が話題にし続けてくれる
💬 最後に|あなたは、誰に応援されたいですか?
「いいね」や「RT」が目的ではありません。
“その人の人生の中に、あなたのブランドが存在し続ける”
そんな関係性こそ、これからの時代における“最強の資産”です。
本章を通じて、売上やツールの話から一歩引いた──
**「信頼の構築設計」**という新しい視点を得ていただけたら幸いです。
🔻 応援いただけると嬉しいです
この記事が少しでも参考になった、共感した、という方は──
ぜひ「スキ」「フォロー」「コメント」で応援していただけると、とても励みになります。
あなたの一つのリアクションが、
次の発信をつくる大きな力になります!
📚 あわせて読みたい:仕組みを強化する関連記事
▶ [第39章|高単価でも売れる“プレミアム戦略”の作り方]
▶ [第40章|サブスクで安定売上をつくる方法論]
▶ [第42章|Web3時代に備える 顧客との新しい関係性]
感情・信頼・関係性の変化にどうマーケティングが対応していくのか──
この3本も、ぜひあわせてご覧ください。
📢 次章予告|【第44章】自己表現とマーケティング ─ “あなたらしさ”が価値になる時代へ
「自分らしく売る」ってどういうこと?
「自己表現=ブランド」になる時代に、何をどう発信するべきか?
次回は、「自分らしさ」と「売れる仕組み」をどうつなげていくか?
自己表現の延長線上にマーケティングを置く方法を掘り下げていきます。
──そんなテーマでお届けする次章も、どうぞお楽しみに!