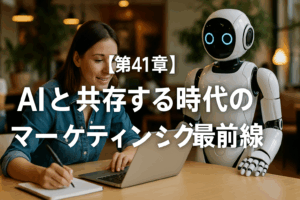Web3時代に備える 顧客との新しい関係性─ 信頼は“所有”から“共創”へ
「つながりが変わる時代」に備える
SNS、LINE、メルマガ、自動化ツール──
テクノロジーの進化で、顧客と「つながる手段」は格段に増えました。
でも、ふと立ち止まってみると、こんな疑問を感じたことはないでしょうか。
「毎日発信してるのに、誰とも“深くつながってる”気がしない」
「フォロワーはいるけど、関係性は浅くて一方通行だ」
「もう“売って終わり”の時代じゃないはずなのに…」
接点は増えたのに、信頼の密度は薄れている。
これは、現代のマーケティングにおいて多くの人が直面している違和感です。
そんな中、次の時代のキーワードとして浮かび上がっているのが「Web3(ウェブスリー)」です。
ブロックチェーンやNFT、DAOといった言葉がメディアを賑わせていますが、
その本質は「新しい顧客との関係性」にあるのではないでしょうか。
🔁 “所有”から“参加”へ、「顧客」が変わる
従来のビジネスは、企業が価値をつくり、顧客がそれを“買う”という構造でした。
ところがWeb3の世界では、顧客が「買い手」から「共創者」へと立場を変え始めています。
- 情報を受け取るだけでなく、自ら発信・編集する
- 商品を買うだけでなく、開発に意見を出し、広める
- サービスを受けるだけでなく、その成長に“参加”する
つまり、「企業 vs 顧客」ではなく、「共に価値をつくる仲間」という関係性が生まれつつあるのです。
📌 Web3が示すのは「信頼のかたち」の再設計
Web3とは技術の話であると同時に、「つながり方の再定義」でもあります。
信用・対話・共感――人間が本来大切にしてきた“目に見えない価値”を、どうやって仕組みに落とし込むか。
この問いに対する一つのアプローチとして、Web3的な思想が注目されています。
これからのマーケティングは、ただ届けるだけではなく、
**「どう信頼されるか」「どう共に歩むか」**に軸足を移していく必要があるのです。
2. Web3とは何か?|マーケティング目線での本質的理解
「Web3って聞いたことはあるけど、正直よく分からない」
「NFTやブロックチェーンって、結局一部の人の話では?」
そんな印象を持たれている方も多いと思います。
ですが、Web3は「テクノロジーの話」ではなく、
“顧客との関係性がどう変わるか”という視点でこそ、理解する意味があります。
まずはその本質を、マーケティング的に噛み砕いて見ていきましょう。
■ Web1・Web2・Web3の違いとは?
| 時代 | 特徴 | 顧客の立場 |
|---|---|---|
| Web1(静的) | 一方的な情報配信(HTML中心) | 情報を“読む” |
| Web2(双方向) | SNS・レビュー・UGCの時代 | 情報を“発信” |
| Web3(分散型) | ブロックチェーンで構築された信頼の仕組み | 情報と価値を“所有・共有” |
Web1が「企業からの一方通行」、
Web2が「誰もが発信できるSNS時代」だとすれば、
Web3は**「個人が“参加者”として対等に価値をやりとりする時代」**です。
■ Web3の3つの中核キーワード
1. 分散型(Decentralized)
企業や中央サーバーが管理するのではなく、
**「多数の参加者が対等な立場でネットワークを構成する」**仕組み。
→ 例:SNSの“いいね”やアカウント管理が1社によるものではなく、
参加者全員の承認に基づくような形。
2. トラストレス(Trustless)
皮肉にも「信頼がいらない設計=裏返すと“信頼できる構造”」。
→ 第三者の仲介がなくても、記録や履歴が改ざんできないからこそ信頼される。
3. ユーザー主権(User Ownership)
データ、コンテンツ、履歴、参加権、報酬──
これまで企業に集約されていたものが、ユーザーの手に戻る。
NFT(非代替性トークン)などはその象徴的な仕組みです。
📌 技術より「思想」が重要
NFT、DAO、ブロックチェーンなど、Web3にまつわる用語は難解に感じられるかもしれませんが、
マーケティングにとって重要なのは、「誰が、どの価値を、どうやって分かち合うのか」という考え方です。
言い換えれば、Web3とはこう言えます:
「ブランドの中心に“企業”ではなく“顧客”が座る構造」
3. なぜマーケティングに影響するのか?
──「売る」から「共に育てる」への構造転換
Web3は、ただの技術トレンドではありません。
それがマーケティングに深く関係するのは、“顧客の立ち位置”が根本から変わるからです。
従来のモデルでは、企業が主導権を握り、
顧客は「選ばれた商品を買う」「サービスを受ける」存在でした。
しかしWeb3の構造では、
顧客が“参加者”であり、“共創者”であり、“価値の担い手”となるのです。
■ 1. 顧客は「買い手」から「ステークホルダー」へ
Web3における顧客は、単なる受け手ではありません。
トークン(報酬)やNFT(所有)といった仕組みによって、
そのブランドやプロジェクトの“当事者”として関わることができるようになっています。
- 参加者としての意見が施策に反映される
- 所有者としての誇りや仲間意識が生まれる
- 成功すれば報酬や利益を分かち合える
これは「応援していたら、評価されて報酬がもらえた」
という関係性ではなく、
「一緒にブランドを育てた」という体験を生むのです。
■ 2. ブランドは「管理」から「共感資産」へ
Web2までのブランドは、統一されたロゴやコンセプト、
緻密に計算されたトーン&マナーによって“守られる”ものでした。
Web3では、ブランドは共感によって共有・拡張されていくものになります。
- DAO(分散型組織)では、参加者が方針や世界観の形成に関与する
- NFTプロジェクトでは、ホルダーが2次創作や派生活動を自由に行う
- ブランドの価値は「共感され、語られること」で成長していく
つまり、**ブランドは企業のものではなく、“みんなでつくる資産”**になるという視点です。
■ 3. 実例に見る、Web3的マーケティングの先行事例
✅ STEPN(ステップン)
“歩いて稼げる”をコンセプトに、NFTスニーカーを使ったトークン経済。
参加者が“遊びながらプロジェクトを育てる”仕組みを構築。
✅ Azuki
NFTプロジェクトながら、ファッション・アート・リアルグッズなど
“ホルダーがストーリーを広げていく”コミュニティ中心設計。
✅ STYLY(スタイリー)
AR・VR領域で“共創者を巻き込んだ空間づくり”を推進。
コンテンツを企業で完結させず、ユーザーが再設計できる世界を展開。
これらの事例に共通しているのは:
- 情報発信者と受信者の垣根がない
- 参加すればするほど、世界観の一部になれる
- マーケティングが“施策”ではなく“体験”になっている
4. Web3時代の「関係性設計」3つのポイント
── 信頼の“つくり方”が変わる
Web3の本質は、「顧客との関係性の再設計」です。
一方的に商品を提供して終わりではなく、
“共に存在し、共に価値をつくっていく”ための仕組みが求められます。
そのために、マーケター・発信者が意識したいのが、以下の3つの視点です。
✅ 1. 一方向ではなく、双方向+自律的な“関わり”
Web3時代のユーザーは、ただ“受け取る人”ではなく、
自ら行動し、他者に影響を与える存在として設計されるべきです。
- コメント・リアクション・リツイートなどの受動的関与だけでなく
- 意見表明、コンテンツ作成、プロジェクト貢献などの“能動的な参加”
そのためには、参加者が“選びたくなる余白”を用意することが大切です。
例:
- あえて未完成な構想を共有して、アイデアを募る
- 「この人がいるから面白くなる」設計で、個の魅力を活かす
- 投票機能や提案受付を開いて、意思決定に関わってもらう
✅ 2. ユーザーとの“共同所有感”を生み出す
モノを売って終わりではなく、**「一緒にこの世界を育てていく感覚」**をどうつくるか。
Web3では、NFTやコミュニティパス、限定アクセスといった仕組みを通じて、
顧客に“役割と居場所”を提供することが可能になります。
例:
- NFTを持つことで、限定チャットや開発チャンネルに参加できる
- プロジェクトに貢献した回数や実績が可視化され、役職が与えられる
- 特典ではなく「帰属と貢献の証」としてトークンを渡す
単なるキャンペーンやポイント制度ではなく、
“その人がいる意味”が構造として伝わる設計が鍵です。
✅ 3. 信頼の“証明可能性”を仕組みに組み込む
これからのマーケティングでは、「信じてください」ではなく、
“信頼できる理由”を明示的に設計することが求められます。
Web3では、ブロックチェーン技術により、
履歴や参加状況、貢献の内容などが「改ざんできないかたち」で記録されます。
これにより:
- どのタイミングでどんな行動をとったか(行動履歴)
- 誰がどの提案に賛成したか(意思の記録)
- 何にどれだけ貢献したか(貢献度の可視化)
──こうした情報がオープンであり、信頼が“説明できる”時代になります。
これは、口コミ・紹介・LTVといった数値では測れない“人間的信頼”を、
透明性と構造で支える方法でもあります。
🎯 まとめ:関係性とは“体験”であり“構造”である
信頼を構築するのに必要なのは、
言葉やサービスではなく、“どんな関わり方ができるか”の設計です。
Web3時代のマーケティングは、まさに**「関係性そのものをデザインする仕事」**とも言えます。
5. まとめ|“選ばれる”から“共に育つ”マーケティングへ
これまでのマーケティングは、
「どうすれば選ばれるか?」を軸に設計されてきました。
しかし、Web3の潮流が教えてくれるのは、
「どうすれば一緒に育てていけるか?」という新しい問いです。
顧客は、単なる“買い手”ではなく、
価値づくりに関わる“仲間”へと変わりつつあります。
📌 共創・共感・共通価値──「共にある」設計へ
Web3的な関係性が示すのは、
技術による効率化ではなく、**“信頼の再定義”**です。
- 情報を届けるだけではなく、一緒に発信する
- 商品を売るだけではなく、世界観を共有する
- サービスを提供するだけではなく、プロセスごと体験してもらう
このような「共にある状態」が、これからのブランドにおける信頼の基盤になります。
🔁 小さな設計から、未来は変わる
大規模なDAOやNFTプロジェクトでなくても、
今すぐできる小さなアクションはたくさんあります。
- 購入者だけが見られる特典ページをつくる
- 意見を募集し、次の企画に反映させる
- 長く関わってくれている人に「称号」や「役割」を与える
こうした“関係性の設計”こそが、ビジネスの強さと継続性をつくっていきます。
🌱 「売上」は、“共に育てる信頼”の結果
マーケティングの本質は、商品を届けることではなく、
**「信頼され続ける関係性をどう築くか」**にあります。
AI、自動化、SNS、そしてWeb3。
テクノロジーが進化するほどに、
“人と人とのつながり”そのものが、唯一無二の価値になっていく。
だからこそ、今私たちが問うべきなのは──
「この人たちと、どんな関係を育てたいのか?」
という、ごくシンプルで人間らしい問いなのかもしれません。
▶ 次回予告|第43章「“シェア・応援”が起点になる価値経済への対応」
Web3以降の世界では、“購入”よりも“共感”が起点になる経済が広がり始めています。
次章では、顧客の応援・紹介・推薦がビジネスの軸になる「価値経済」の本質と、
それに対応するマーケティングの新たな役割について掘り下げていきます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
Web3というと難しそうに聞こえますが、
本質は“人と人のつながり方”を、もう一度見直すことにあります。
あなたが届けたい価値を、誰と、どう育てていくのか?
この問いへのヒントが、少しでも見つかっていたら嬉しいです。
記事が参考になった方は、ぜひスキ・フォロー・コメントを通じて応援いただけると励みになります。
▶ 次はこちらもおすすめ:「応援が価値になる時代」へ──
【第43章】“シェア・応援”が起点になる価値経済への対応(近日公開)