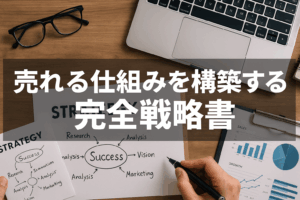【第1回】マーケティングとは何か?売れる仕組みを科学する基礎と戦略的視点
〜デザイン・Web・EC業界の広報担当が最初に知るべき本質〜
「いい商品が売れないのは、あなたのせいではない」
「クオリティには自信がある。デザインにもこだわった。けれど、まったく反応がない…」
Web制作会社やECブランド、デザイン事務所の現場から、そんな声を耳にすることは珍しくありません。
実はそれ、**よくある“つまずき”**なのです。
なぜなら、現代の市場では「良いものを作れば売れる」という常識が、すでに通用しなくなっているから。
代わりに求められているのが、“売れる状態”を意図的に設計する力=マーケティング力です。
あなたのビジネスが伸び悩む理由は、商品力ではなく「届け方」にあるかもしれません。
この連載では、そうした課題を抱える方々のために、マーケティングの本質と実践方法をやさしく、しかし本質的に解説していきます。
1章|マーケティングとは?定義から理解する“売らずに売る”技術
1-1. マーケティングの定義を疑え
多くの人が「マーケティング=広告や宣伝」と誤解しています。
確かに広告やSNSは手段の一つではありますが、それは**“木の枝葉”の部分に過ぎません**。
マーケティングの本質は、顧客の理解と売れる仕組みの設計です。
1-2. ドラッカーの定義に見る「究極の理想」
「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである。」──ピーター・ドラッカー
この言葉の核心は、「売り込まなくても売れる仕組みをつくる」ということ。
たとえば、あるデザイン会社がInstagramで発信していた自社事例に共感した中小企業の経営者が、「このテイスト、うちのブランディングにぴったりだ」と感じ、自然と問い合わせをしてくる。
この“導かれるような購買行動”こそ、ドラッカーの言う理想の姿です。
1-3. コトラーの定義で見る「顧客価値の中心化」
「マーケティングとは、顧客のニーズを見つけ、それを満たす活動である。」──フィリップ・コトラー
マーケティングとは、自分の商品を“売り込む”ものではなく、相手が求めているものを“届ける”ための活動。
売れる理由を考えるのではなく、「なぜ、あの人が買う気になったのか?」を掘り下げるのです。
1-4. 日本企業のマーケティングにおける課題
2022年の電通「B2Bマーケティング実態調査」によると、日本のBtoB企業のうち、自社に専任マーケティング担当がいる割合は約28%に留まるとされています。
また、マーケティングを「売上と結びつけるのが難しい」と感じている企業も多数。
このように、マーケティングは「曖昧なもの」「属人的なノウハウ」という認識が根強く、体系的に学ばれていない分野でもあるのです。
2章|マーケティングの目的:「売れる仕組み」のデザイン
2-1. セールスとの違いを明確にしよう
| 項目 | セールス | マーケティング |
|---|---|---|
| 目的 | 商品を売る | 売れる状態を作る |
| 主体 | 営業担当者 | 組織全体・仕組み |
| フェーズ | 販売の“後半” | 販売の“前半” |
| 例 | 見込み客への提案・訪問 | LP設計、広告、導線設計、コンテンツ設計 |
たとえば、営業が訪問して初めて商品を説明するのではなく、その前にすでに関心を持ち、購入イメージまで出来上がっている。
マーケティングはそんな状態を作る“戦略設計”です。
2-2. ファネル思考:購買までの“心理の段階”を意識する
「ファネル(漏斗)」とは、ユーザーが購買に至るまでのステップを、段階的に捉えるフレームワークです。
- 認知:存在を知る
- 興味・関心:自分ごとになる
- 比較・検討:競合と比べる
- 行動:購入・申し込み
- 継続・紹介:リピーターや推奨者になる
各段階で必要な情報、接点、信頼形成の手段は異なります。
例:EC向け商品なら「1:SNS広告→2:特集記事→3:導入事例→4:LP→5:サンクスメール+レビュー依頼」
このように、段階に応じた戦略的アプローチの設計が売上に直結します。
3章|誰に・何を・どうやって届けるのか?
3-1. 誰に届けるのか?──ターゲティングの精度がすべてを決める
Web制作会社が「どんな企業でも対応可能です」と言ってしまえば、それは誰の心にも響かない表現になります。
むしろ、「EC事業者向けLP制作に強い」「美容業界専門のブランディング」などの尖った訴求の方が刺さりやすいのです。
3-2. 何を届けるのか?──“価値”を言語化する
自社が提供している“商品”の中に、どのような「価値」があるかを明確にしましょう。
- スペックの羅列ではなく「どう役に立つのか」
- 一見当たり前なことでも「他社とどう違うのか」
例:デザイン会社が「テンプレではなく、ヒアリングから作り上げる独自設計」を前面に押し出す
このように、商品ではなく「顧客にとっての意味」を伝えることで初めて価値が届きます。
3-3. どうやって届けるのか?──チャネル選定と導線設計
届ける手段=チャネルは目的に応じて選ぶべきです。
| チャネル | 特徴 | 向いている目的 |
|---|---|---|
| Web広告 | 短期でアクセスを得やすい | 認知拡大/検証 |
| SEO記事 | 中長期での資産 | 信頼獲得/ナーチャリング |
| SNS運用 | 拡散性・接触頻度が高い | ファン獲得/共感形成 |
| セミナー | オフラインやZoomなどで双方向性 | 検討層への深掘り情報 |
たとえば、「初回接点はSNS → 記事に誘導 → ダウンロード資料でリード獲得 → メールで関係構築」という流れは非常に一般的で効果的です。
4章|BtoBマーケティングのリアル──“売れない”3つの原因と処方箋
4-1. BtoBマーケティングが難しい理由
BtoCに比べ、BtoB領域でマーケティングが機能しづらいのは、主に以下のような構造的要因があります:
- 意思決定者が複数いる
→ 営業部長・経理・経営者など、立場によって関心が異なる - 検討期間が長い
→ 「すぐに買う」はほぼなく、数週間〜数か月に渡って比較される - 感情ではなく合理性が優先される
→ デザイン性よりも、費用対効果・社内説得材料が重視される
つまり、単なる「魅せ方」ではなく、“信頼できる理由”を論理的に示す情報設計が求められるのです。
4-2. 失注しないための3つのポイント
- 課題を顕在化させるコンテンツ提供
→ 導入前の「気づき」を促す記事やチェックリスト - 業界特化の事例を見せる
→ 汎用的な実績ではなく、「御社に近い企業の成果」の提示 - 比較・稟議に強い“資料設計”
→ 「他社との違い」「価格だけで比較されない工夫」がある資料が有効
例:あるWeb制作会社は、BtoB企業向けに「営業不要なLPの仕組み化」というフレームで成約率を倍増。
社内稟議を通しやすいように「社内共有用の簡易資料」も別途提供したことで意思決定が加速。
5章|売れる状態をつくる「3ステップ構造」とは?
5-1. ステップ1:集客(リードジェネレーション)
この段階で意識すべきはターゲットの“入り口”を複数持つこと。
- SEO記事(指名検索・課題検索の受け皿)
- SNS(共感・認知獲得)
- セミナー・展示会(信頼形成と直接接触)
- Web広告(顕在層の刈り取り)
ポイントは、**「なんとなく」ではなく「設計された入口」**であること。
1クリック後に“どんな体験をしてもらうか”まで設計して初めて、マーケティングの機能を果たします。
5-2. ステップ2:ナーチャリング(関係性の構築)
BtoBにおいては、初回接触での即成約はまれです。
ここで有効なのが、段階的に接触して“信頼”を積み上げる施策。
- ステップメール(シナリオ設計)
- 導入事例の共有
- 定期ニュースレターや業界トレンド
- セミナー・コンサル付き相談窓口の案内
あるEC支援企業は、無料ダウンロード資料の登録後に「3週間限定のノウハウ配信メール+個別相談会案内」をセットにしたことでCV率を1.5倍に向上。
5-3. ステップ3:商談・クロージング(意思決定の支援)
営業部門との連携が肝になります。
ここでマーケがすべきは、“営業がやりやすい状態”を整えること。
- 問い合わせ前の情報提供
- ヒアリング用の事前フォーム(条件付きCV)
- 自社紹介資料、競合比較表、FAQの整備
6章|マーケティングに潜む“落とし穴”とその回避法
6-1. 「誰にでも売れる」は、誰にも売れない
ターゲットの定義が曖昧な状態で発信しても、言葉もメッセージもボヤけてしまいます。
×:「中小企業向けにITサービスを提供します」
○:「従業員10〜30名の小売業が、アナログ管理から脱却するためのクラウド顧客管理ツール」
対象を絞るほど、伝わる力は強くなるのです。
6-2. コンテンツが“日記化”してしまう
ありがちなのが、社内報のような近況報告だけの記事。
顧客の課題に刺さる視点が抜け落ちていると、いくら更新しても効果は出ません。
- タイトルに課題ワードを含める
- 数値や事例で信頼性を加える
- 読後に行動したくなる“次のステップ”を示す
この3点だけでも、大きく改善します。
6-3. マーケと営業の“分断”
マーケティングでどれだけリードを集めても、「営業が活用できない」と失注につながります。
- 営業がほしい情報(課題感・導入タイミング・競合状況)を共有
- 見込み度のスコアリングを明示
- 定例会やチャットでの即時フィードバック体制
マーケと営業が連携することで、獲得から受注までの滑らかな流れが生まれます。
7章|明日からできる「実践マーケティング」の第一歩
7-1. ペルソナを“現実”に引き寄せる
空想上の人物ではなく、既存顧客や過去の相談者からリアルな情報を抽出して設計します。
| 項目 | 例(Web制作会社の場合) |
|---|---|
| 業種 | EC運営企業(年商2〜5億円) |
| 課題 | 売上はあるがCVRが低く、広告費の回収が不安定 |
| 決裁者 | 経営者またはマーケ責任者 |
| 情報源 | Instagram/Google検索/展示会 |
7-2. 自社の“隠れた価値”を再定義するワーク
- 「なぜ過去の顧客はあなたを選んだのか?」を3つ書き出す
- 他社との違いを“数字・方法・人柄”の切り口で洗い出す
- それを簡潔な言葉に置き換え、1行で説明できるようにする
7-3. 小さく試して、反応を見て改善する
すべてを一度にやる必要はありません。
- SNSでの投稿にCTAを加える
- LPのボタン文言を変えてみる
- セミナー資料を「見せる資料」から「読ませる資料」へ変える
PDCA(Plan-Do-Check-Act)の小さなループを繰り返すことで、マーケティングの設計力は鍛えられていきます。
8章|まとめ:「売る」のではなく、「買われる状態をつくる」
マーケティングとは、「モノを売る活動」ではなく、「売れる状態をつくる構造設計」です。
そのために必要なのは、次の3つ:
- 顧客理解(誰に・どんな課題があるか)
- 価値の言語化(なぜそれが解決策なのか)
- 流れの設計(どうやって出会い→検討→購入につなげるか)
特にWeb・デザイン・EC業界のように競合が多い分野では、差がつくのは“届け方”の質です。
9章|次回予告:「売れる商品設計」の基礎──ニーズとウォンツを見極めよ
次回は、マーケティングの根幹である「ニーズ」と「ウォンツ」について解説します。
- 人がなぜ“買う気になる”のか?
- 商品が“売れない理由”は価値がないからではない
- 欲望と課題を分けて設計する「ニーズマップ」の使い方
を、事例とともにお届けします。